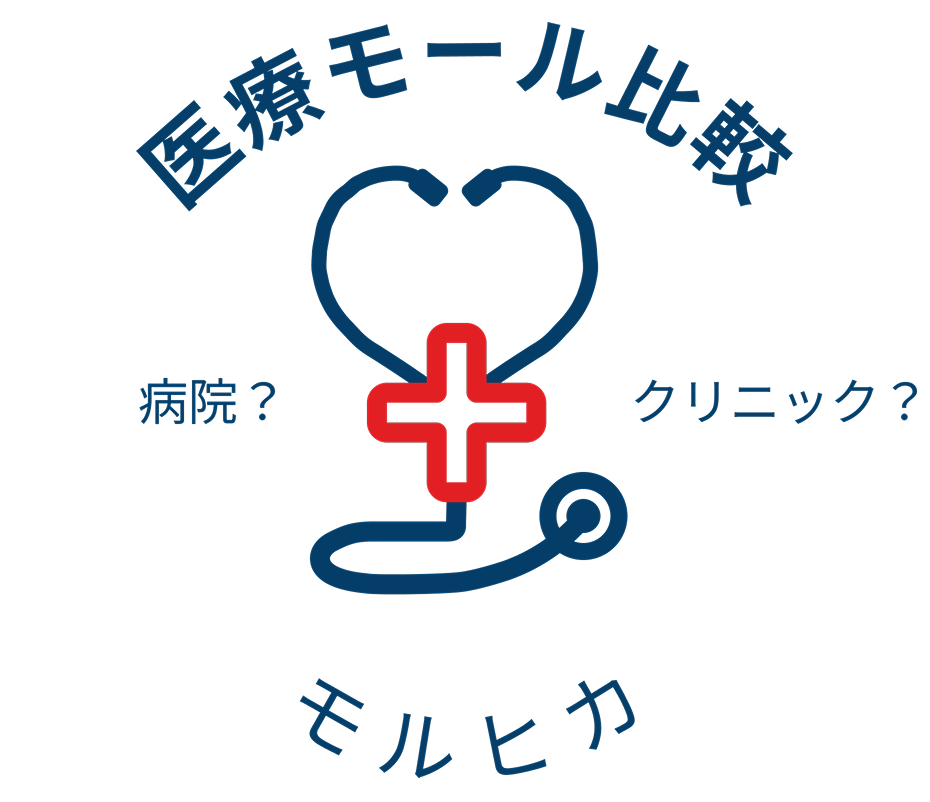メリット・デメリットを徹底解説!

03 医療モールの現状
冬の時代を迎えた医療モールの惨状

ここからのお話は少し硬いですが、医療モールのなりたちをお知り頂いたほうがよいと思いますので、書かせて頂きます。
日本で最も早い時期に医療モールは、1985年のアイセイ薬局行徳店だと言われております。当時は医療モールというコンセプトはなかったと考えられますが、アイセイ薬局は耳鼻科と小児科を誘致して成功をおさめたといいます。仮に1985年を医療モールの誕生年だとすれば、すでに40年を超える歴史があることになります。
しかしながら、日本で医療モールというコンセプトが登場しはじめたのは1990年代末、広く注目を集めるようになったのは2000年代に入ってからであると考えられています。日経テレコンで医療モール・クリニックモール及びメディカルモールという用語を検索しますと、初出は医療モールが2000年8月、クリニックモールが1997年4月、メディカルモールが1997年8月でした。記事数は、医療モールが383件、クリニックモールが42件、メディカルモールが47件です(いずれも2016年8月30日分まで検索)。2000年前後に医療モールというコンセプトに注目があつまり、そのコンセプトに基づく医療モールオープンのブームが2003~2004年頃に訪れました。日本能率協会総合研究所の推定によれば、2003年の医療モールの市場規模は568か所223億円ですが、2005年には1,155億円へと急拡大しています。2007年の時点ですでに医療モールは1,000カ所を超え、毎年の診療所の新規開設数の10%程度を占めるようになりました。新規開設の傾向は現時点でもそれほど変わっておらず、とりわけ薬局や不動産事業者による医療モールの新規計画が目立つようになってきています。医療モールの増加傾向は、2015年にはじまった厚生労働省主催の「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」にて提唱されたプライマリ・ケアの拠点機能を有する薬局ニーズにより、ますます強化される可能性があります。日本全体で医療やヘルスケアに関わる費用が増大している中で、医療モールはその費用低減の一つの有効な手段となりえる可能性があります。
しかしながら、医療モールは全体として増加傾向にあるにもかかわらず、2000年代中頃よりすでにその経営的なリスクや問題点が指摘されてきていました。たとえば、経営ノウハウの持たない医師をターゲットとした詐欺まがいの医療モール計画もあれば、通常よりも割高のコンサルティング費用を要求する企業などが少なくないことが、すでに2007年に指摘されていました。

後述するクリエイトSDホールディングスが経営するクリエイトSD薬局医療モールなどが、この典型です。
クリエイトSDホールディングス医療モールでは過去にあちこちの医療モールで入居者の一斉退去や、信じられないことに医師に食わせてもらっているクリエイトSDホールディングスが入居医師を裁判に訴える事例が多数生じています。
急速なオープンによる競争激化や医師不足により、2010年頃より医療モールの経営母体の倒産や破産もみられるようになりました。
「医療モール冬の時代」(週刊ダイヤモンド)
https://diamond.jp/articles/-/8117文中をご紹介いたしますと
『都心部では医療モールが乱立気味となり、かつてのような目新しさと集客効果がなくなりつつある。ほかに患者を紹介せずに、患者を囲い込むことも多い。ある医療コンサルタントは「たとえば、花粉症ならば、耳鼻科や眼科には行かずに、行きつけの内科ですませてしまう患者が大半である。医療モール内で複数の診療を受診する患者は10%もいたら多いほうだ」と指摘しています。
少なくとも単なる
医療モールという形態だけで、医師や患者が集まる時代は終わったことは確かだろう。』と。

結論:時代遅れの医療モールに夢を見ない
医療モールが成功しない要因
クリニックの連携不足
クリニックや医師の誘致の失敗
見込み通りの集客が得られない
コスト削減効果が薄い
などです。
こうした課題を解決しない限り、医療モールというコンセプトが社会の期待に十分に応え、需要=患者や住民と、供給=医師や薬剤師や運営企業の双方が満足できる結果を得ることはできません。これらの問題はいずれも、医学よりも経営学が解決すべき課題です。
医療モールで成功するには医師にも経営センスが必須であるといえましょう。