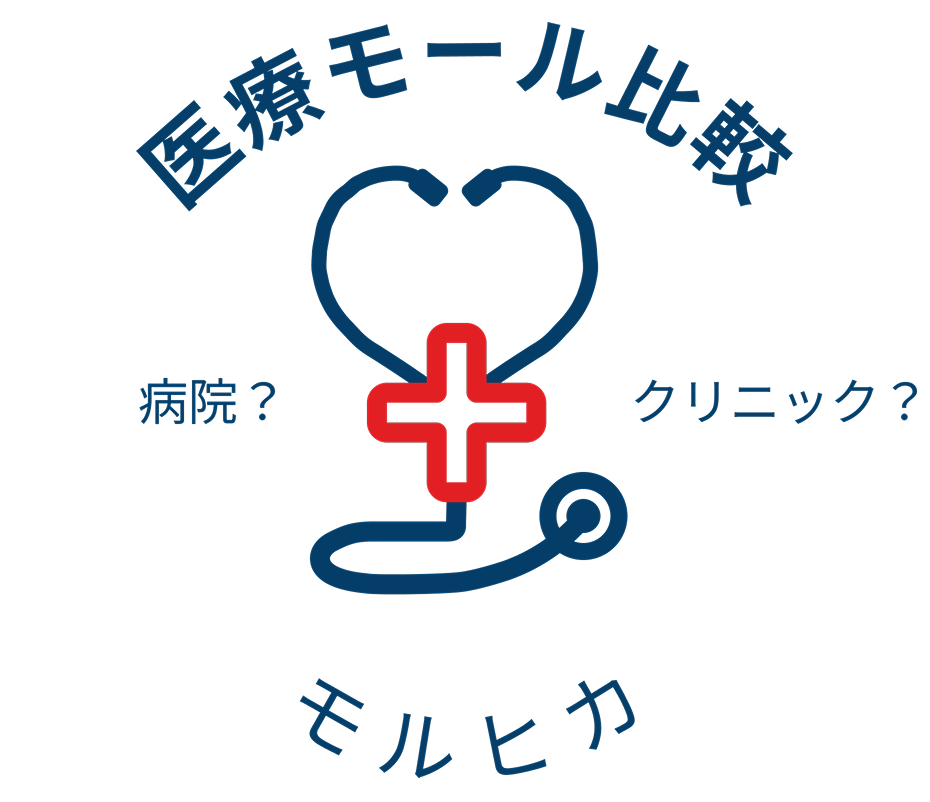メリット・デメリットを徹底解説!

02 医療モールの形態

医療モールの形態は、おおよそ以下の3形態に類別されます。
A.医療モール特化型施設
世間的には、この形態を医療モールと認知される方が多いと思います。
入居者はクリニック・薬局のみです。
クリニック開業仕様の建築設備のため、電気容量・給排水・床荷重などがクリニックに適しています。
広さも入居させたい標榜科目を想定して造られており、ハード面では安心して開業準備を進められるタイプといえるでしょう。
このタイプの医療モールは、複数の標榜科目が入居するため、医療モールとしての価値も高まります。
メリット:地域住民も、「医療モール」として認知されやすい傾向にあります。
デメリット:診療科目が重なると患者の奪い合いに。
トラブルクリニックがあると、患者が散るというトバッチリを受けるアナジー効果
B.医療ゾーン
聞きなれないかもしれませんが、いわゆる医療版フードコートです。
複合商業施設内の一角のエリアに、複数の標榜科目が集められています。
メリット:高い認知度が見込めます。
スーパーマーケットや小売店、保育園や塾などが入っているため、普段からその施設を利用する方に広く知ってもらうことができ、またお買い物などのついでに来院してもらえることもあります。
ハード面では、施設の駐車場やお手洗いを共用できるという点もメリットのひとつです。
デメリット:医療ゾーン型に入居した医療機関の患者単価は低い
人は毎日、車に乗って、家族を載せて大きな駐車場から距離の複合商業施設に行くでしょうか?
せいぜい週1度です。
足のない高齢者は通えないので、結局家から近い診療所に通います。
すなわち、複合商業施設に開業しても、結局は近くの人しか通わないのです。
さらには施設が大きいだけ、車を止めて診療所まで歩く距離が長く不便ですから、後述する特定疾患・生活習慣病を患う高齢者の来院は期待できません。患者はたまに風邪をひいたりお腹をこわす程度の普段は元気な人ばかり。
Y博士が『10.開業以前に備えるべき最も大切なこと』のなかで後述する診療単価の高い高齢者や生活習慣病の患者は意外と少ないものとなります。
C.医療ビレッジ
聞きなれない言葉かもしれませんが、地主などが建物を建て、複数の標榜科目を募集する形態です。
郊外のロードサイドに多く、近隣の郊外型商業施設からの誘引を目指します。
メリット:複数の標榜科目からのシナジー効果
近隣の商業施設から患者が呼び込める
デメリット:医療ビレッジに入居した医療機関の患者単価は低い
医療モール特化型と同様に、標榜科目の重なりで患者の奪い合いや
トラブル医療機関によるアナジー効果
車を運転して通うことが原則となりますから、複合商業施設同様、後述する特定疾患・生活習慣病を患う高齢者の来院は期待できず、診療単価の高い高齢者や生活習慣病の患者は意外と少ないものとなります。
一見するとどの医療モール形態も魅力的に見えますが、正常性バイアスに陥ってはいけません。
シナジー効果よりも、負の相乗効果、すなわちアナジー効果を予測して対応する必要があります。
医療モールに入居されて間もなく愕然とすることがあります。

それは入居医療機関同士の共食いです。
同居他院が先生の専門分野を侵食するのです。トラブルクリニックがないとしても、先生が眼科で開業なさったと致しましょう。目薬を処方するのは医療モールのなかで先生だけに限定できるでしょうか?
答えはノーです。
目薬は内科でも精神科でも処方可能です。
他方眼科でも患者の利便性を考え、風邪薬を処方します。内科でもシップや痛み止めを処方します。
大学病院とは違います。「あ~目薬?点眼薬は眼科だからッ!」とはならないのです。
結論:医療モールでは、他科との共食いがあり、勝ち組だけが儲かる
しかし、本当に儲けているのは誰でしょうか?
ここまでお読みになって、まだピンと来ない先生がたのご開業はまだ早いと思います。
しかし、その儲けているはずの胴元である医療モール側も経営状況は厳しい時代を迎えているのです。